Infrastructure
Issue Date: 2021-10-21 コミュニティサービスにおけるレコメンデーションの変遷とMLパイプラインについて, PyCon'21 Comment
・ママ向けのQ&AサービスにおけるレコメンドとMLパイプラインについて紹介
◆レコメンドエンジンの変遷
・Tensorflowで実装したMFから始まり、その後トピックを絞り込んだ上で推薦するためにLDAを活用したレコメンド、最終的にSoftmax Recommendationを開発
* Softmax Recommendation:
https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/dnn/softmax
* ユーザプロファイル(e.g. 行動ベクトル, ユーザの属性情報)等を入力とし、hidden layerをかませて最終的にアイテム次元数分のスコアベクトルを得る手法
* 行動ベクトル=ユーザが過去にクリックしたQ&Aだが、質問ベクトルを得るために内容テキストは利用せず行動ログ+word2vecで学習
* 類似質問検索による定性評価の結果良い結果、関連質問を抽出できるベクトルとなっていることを確認
→ レコメンド手法の変遷につれ、ベンチマークを上回るようになっていった
◆MLパイプラインについて
・AWS Step FunctionsとAmazon Sagemakerを利用
・AWS Step Functions
* AWS上の様々なサービスをワークフローとして定義できる(json形式でワークフローを記述)
・Amazon Sagemaker
* 機械学習向けのIDE
* notebook上でのデータ分析・モデル学習、実験管理や学習済みモデルのデプロイが可能
* Sagemaker Processingを用いることで、実行したい処理やインスタンスタイプを指定することで、notebookとは別の実行環境(コンテナ)で任意のpythonスクリプトを実行可

・ワークフローの定義=AWS Stepfunctions, スクリプト実行のリソース=Sagemaker Processingとして利用
MLパイプラインについては下記資料により詳しい情報が書かれている
https://speakerdeck.com/takapy/sagemaker-studiotostep-functionswoyong-itemlopshefalse-bu-wota-michu-sou
#Article #Tutorial #Pretraining #NLP #Dataset #LanguageModel #PostTraining #Selected Papers/Blogs
Issue Date: 2025-10-31 The Smol Training Playbook: The Secrets to Building World-Class LLMs, Allal+, HuggingFace, 2025.10 Comment
元ポスト:
#Article #MachineLearning #LanguageModel #GenerativeAI #Slide #read-later #One-Line Notes
Issue Date: 2025-09-28 AIインフラを考える, Masayuki Kobayashi, 第38回 ISOC-JP Workshop, 2025.09 Comment
元ポスト:
KVCacheサイズとデータ転送量の部分はパフォーマンスチューニングの際に重要なのですぐにでも活用できそう。前半部分は私にとっては難しかったので勉強したい。
データタイプやユースケースに応じてAWS上のサービスなどをマッピングしてくれているチートシート。わかりやすい。
#Article #AWS #AWSLambda Issue Date: 2023-04-23 Lambda tips Comment
- AWS Lambda and EFS Troubleshooting
-
https://www.digitalsanctuary.com/aws/aws-lambda-and-efs-troubleshooting.html
- VPC内のEFSにアクセスできるようなセキュリティーポリシーを作成してアタッチすると良いという話。in-bound, out-boundともにNFSを許可
- 【AWS】VPC Lambdaを構築したときのメモ
-
https://qiita.com/aiko_han/items/6b3010250e2887206b4f
- Amazon VPC に接続されている Lambda 関数にインターネットアクセスを許可するにはどうすればよいですか?
-
https://repost.aws/ja/knowledge-center/internet-access-lambda-function
#Article #AWS #ECS Issue Date: 2023-04-16 ECS tips Comment
- キャパシティプロバイダーについて
-
https://dev.classmethod.jp/articles/regrwoth-capacity-provider/
- Fargateをスポットで7割引で使うFargate Spotとは? #reinvent
-
https://dev.classmethod.jp/articles/fargate-spot-detail/
- ECSでのデプロイでコケる原因ざっくりまとめ
-
https://zenn.dev/isosa/articles/e371bc2d76e812
- M1 MacでビルドしたイメージをFARGATEで使おうとした時の'exec user process caused: exec format error' の対処法
-
https://qiita.com/ms2geki/items/1cfb0db3f4c1aab96e75
- PythonでログをCloudWatchに出力する「Watchtower」
-
https://dev.classmethod.jp/articles/python_log_cloudwatch_watchtower/
#Article #Tools #MLOps #Blog #Repository Issue Date: 2022-12-01 deploy-API-to-GCP Comment
FlaskAPIを(Flaskでなくても良い)Google Cloud Run上で、TerraFormで定義したインフラ環境でデプロイするためのリポジトリ
0. リポジトリをclone
1. Flaskアプリ作成
2. FlaskアプリをDocker化
3. TerraFormのStateを保存するためのCloudStorage作成
4. TerraFormのコード作成
5. GitHub Actionでデプロイ(CI/CD)
5によってmainブランチに対するプルリクが本番環境にデプロイされる。
Cloud Runについて
https://dev.classmethod.jp/articles/gc-cloud-run/
#Article #MLOps #Blog Issue Date: 2022-04-27 MLOps: 機械学習における継続的デリバリーと自動化のパイプライン, Google Comment
機械学習(ML)システムの継続的インテグレーション(CI)、継続的デリバリー(CD)、継続的トレーニング(CT)の実装と自動化
MLOpsのレベルを0~2で表現しており、各レベルごとに何が達成されるべきかが図解されている。


#Article #Tutorial #MachineLearning #Pocket Issue Date: 2021-10-19 Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems, Sculley+, Google Comment

よく見るML codeが全体のごく一部で、その他の基盤が大半を占めてますよ、の図
#Article #AWS Issue Date: 2021-10-08 データレイクのつくりかた、つかいかた、そだてかた, 関山宜孝, AWS Summit Comment
こちらも参照のこと
https://logmi.jp/tech/articles/324242
◆伝統的なデータウェアハウスの限界:
場当たり的にデータを蓄積し、活用しているとデータのサイロ化が生じてしまう。
サイロ化したデータを一箇所にまとめて活用できるようにしましょうというのがData Lakeの考え方。
◆データレイクアーキテクチャ
すべてのデータを一元的に保管でき、
耐障害性、可用性が高く、スケーラブルで低コストな必要がある。
また、データは非常に多様化しているので、多様なデータをそのままのフォーマットで保管し、
活用できる必要がある。
ストレージとデータの活用層を疎結合にして、さまざまなユースケース・分析に対処できるようにする。
(たとえば、ストレージに特定のスキーマのテーブルを使っており、そのスキーマに対してしか分析できません、とかは避けるということかな?)
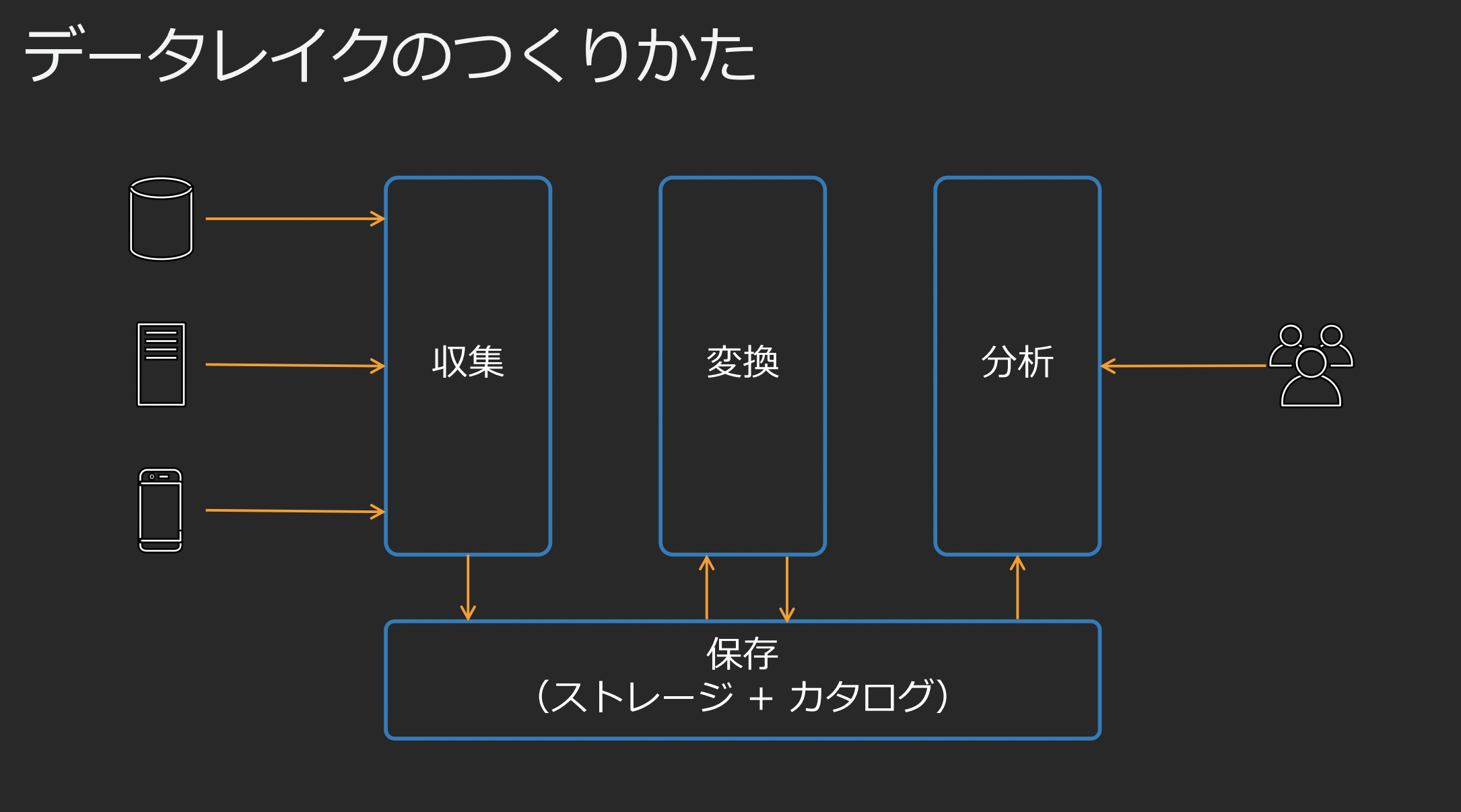
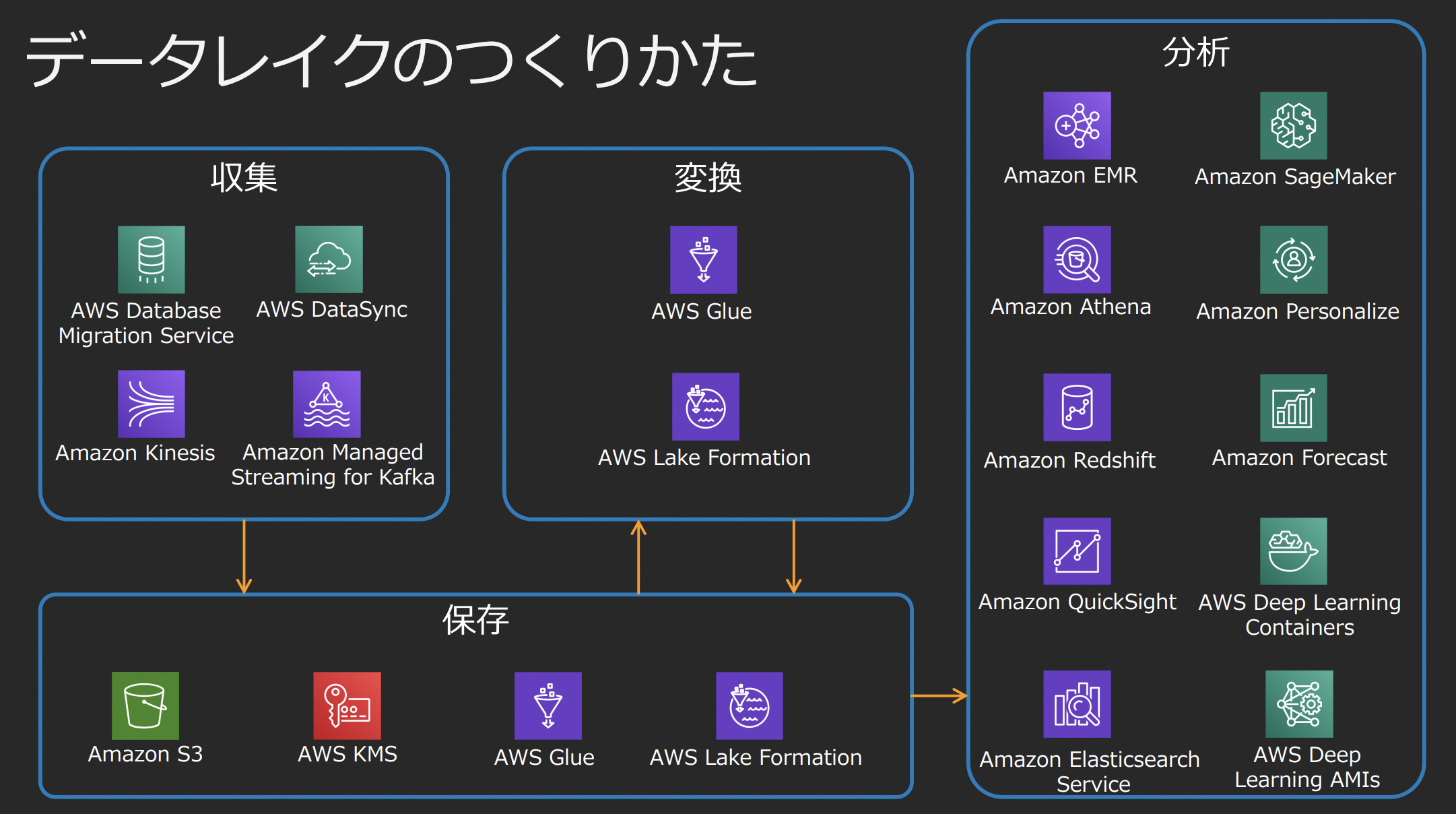
S3上に生データを保存し、AWS Glueでメタデータを管理する。AWS GlueのようなETLサービスを利用してデータを利用しやすい形式に変更して格納し、活用する。
データレイクを作る際のポイント「小さく始める」という部分も重要だと思われるので参照のこと
#Article #MachineLearning #MLOps #Blog Issue Date: 2021-06-18 NVIDIA TRITON INFERENCE SERVER, 2021 Comment
Nvidiaのオープンソースのinference server
モデルのデプロイや管理、スケーリング等を良い感じにしてくれるフレームワーク?
